[PR] 当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。
こんにちは! イッキュウです。
このブログでは1級・2級及び全種目(建築・土木・ 電気工事・管工事・電気通信・造園・建設機械 )施工管理技士の合格メソッド(対策、勉強法、勉強時間、モチベーション管理)を解説します。
今や、知識なし・未経験の種目でも合格する自信があります(未経験の種目は受験が出来ませんが、もしも出来たと仮定したら・・の話です)
他の種目の問題は全て確認しました。
そして「1級・2級、全種目、合格メソッドは全て同じ!」と、結論付きました。
- 施工管理技士検定で合格したい方
- 1級・2級
- 建築/土木/管工事/電気通信/電気工事/建設機械
- 対策や勉強法を知りたい方
- スクール・通信講座・添削
- オススメの問題集
- 勉強時間
- モチベーションの維持
ちょうど令和3年度の制度改定もわかり、従来通りの過去問学習で良いと確認出来た所です。これは良いタイミングと考えました。
※当勉強法は本やサイトで試行錯誤の上まとめたものです。特に良い参考文献は次にまとめました。
》【受験・資格・人生】を独学で乗り切る勉強法・おすすめ本6選
最初になぜ全種目・対策が共通で良いのか説明しておきます。
なぜ、種目が異なっても同じ方法でいいのか・・?
当ブログでは1級建築・1級土木・1級管工事を独学・経験談を紹介しています。結果としてどの種目も勉強法は同じでした。
そこで、なぜ試験運用や内容で共通点が多いのか考えてみました。
✔ 国土交通省が全てを所管しているから

「施工管理技士」は建設業法、つまり法律で定めらた技術検定であるため、検定の骨格・根本は全種目同じだからです。
国土交通省は、建設工事に従事する技術者の技術の向上を図ることを目的として、建設業法第27条の規定に基づき技術検定を行っています。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000055.html
例えば、高卒や、大卒が必要な経験年数はどの種目も同じです。
また、受験3ヶ月前に申し込み、第一次検定があり、1ヶ月後に一次の合格発表、その数カ月後に第二次検定、その3ヶ月後に二次の合格発表という流れも同じです。
試験運用する公益団体も3社しかなく、複数を担当しているところもあります。
| 検定種目 (1級・2級) | 指定試験機関 |
| 土木,造園, 管工事, 電気通信工事 | (一財)全国建設研修センター https://www.jctc.jp/ |
| 建築, 電気工事 | (一財)建設業振興基金 https://www.kensetsu-kikin.or.jp/ |
| 建設機械 | (一社)日本建設機械施工協会 https://jcmanet.or.jp/ |
✔ 資格ではなく「検定」だから
施工管理技士の技術検定は「資格」ではありません。国家の「検定」です。
「検定」とは辞書によると「一定の基準を設け、基準に適合するかどうかを検査し、合格・不合格・等級・価値などを定めること」です。
つまり、ある水準にあるかどうかを過去の問題難易度や、関連資格と水準をあわせながら、公平にチェックするということです。
このため、難易度は過去の整合性(つまり過去問)を重視し、類似する検定は横断的に整合性を重視するわけです。

それでは本題にはいります!最初に結論を示してから具体的に見ていきます。
施工管理技士・合格メソッド・結論!

最初にざっくりと結論(概要)をまとめます。
この方法で「やる気さえあれば」誰でも、忙しくても、合格出来ます。

「やる気はさえあれば」にひっかかかるなら具体的に言います。2級で150hr前後、1級で200hr前後の勉強をすると決意できる程度の「やる気」です。
「検定問題」は英・数・国のようなセンスは不要。記憶中心の理科や社会の問題と捉えたら良いです。また、問題の構成は、過去問そのままか、類似問題です。
したがって、だれでもこの程度の時間をかければ合格レベルに仕上がって来ます。
※これに関しては後で詳しく解説します。
過去問をやっては解説を読み、論述は必要に応じて添削をお願いすればいいだけですからね。
※添削サービスは1万円程度で実績あるサービスがあります。
独学or 添削or 通信講座or 資格スクール?

受験を決意した時、どのようにして学ぶかを決める必要があります。
オススメは独学を基本として、添削サービス受けることです。コスパも合格率も高いです。
ただし、独学は自信がなかったり、会社からスクールの経費が出る場合は使うことも有りです。次に詳しく見ていきます。
✔ 勉強方針は大きく3つに分けて見る必要がある
勉強方針を決める前に大きく3つに分類し、それぞれで方針を立てていく必要があります。
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 第一次検定 | 第二次検定 | 第二次検定 |
| マークシート | 記述式問題 | 経験記述 |
| 主に4肢1択 | 主に記述 | 論述 |
試験内容は過去問中心ですのでⅠ、Ⅱは独学で何とかなります。
実際に勉強を始めればわかるのですが「Ⅰ」は簡単であり独学で合格可能です。これは言い切れます!
※一次では余計なお金をかけないことです。
一次が独学で突破できないようであれば、二次のⅡ、Ⅲは厳しいかもしれません。二次は記述問題となり、一次の数倍難しくなりますからね。
✔ ポイントは第二次検定です。
第二次検定は急角度で難易度が上がります。
一発で決めたいなら、ここから外部サービスを検討するのは合理的判断です。ざっくり以下の表で掴んで下さい。
| 独学 | 論述添削 | 通信講座 | スクール |
| 3~4千円 | 0.6~3万円 | 1.6~8万円 | 7~40万 |
| ややリスク有り | コスパ最高 | リーゾナブル | 合格率80%超 |
※詳しくは次にまとめました。
》【経験記述】対策を徹底調査!コスパの良い順にランキングで紹介
二次の記述問題も難しめですが過去問学習で対応出来るので、答えや採点基準がブラックボックスな論述のみ添削を受けるのがオススメです。
オススメのサービスは以下の通りです。
▶ 独学サポート事務局 ※2022年度試験対象・早期割引キャンペーン有り
施工管理技士・合格のための勉強時間

次に申し込みから合格発表までの流れを見た上で、一次、二次に必要な勉強時間を解説します。
申し込みから合格発表までの流れ
1級建築を例にとって受験の流れを紹介します。どの種目も1級・2級も概ねこの流れです。
- 2月初旬決断!申し込み
まずは迷いを断ち切って決断することが何よりも大事。特に独学で合格目指すなら。
- 3月~第一次検定の勉強開始
問題集を手に入れて過去問7年分を2~3周します。
- 5月下旬受験票が届く
受験表が届くのは約2週間前。知らないと「なかなか届かないなぁ」と焦ります。
- 6月中旬第一次検定
令和3年度より新問題が追加されましたが、従来通りの勉強でOKでした。合否は自己採点で翌日分かる。
- 7月~8月二次の「経験記述」の勉強開始
問題集を手に入れて第二次検定の「経験記述」の作成とチェック。
- 7月中旬一次の合格発表,二次の申し込み
合否の書面は数日で届きます。二次も入金・申し込みが必要。忘れずに!
- 9月~10月二次の「記述式問題」の追込み
過去問10年分を4~5周程度。とにかく書いて覚えます。
- 9月下旬二次の受験表が届く
経験記述は第三者のチェックも。記述式問題はセルフ模試で進捗度を確認。ここからは体調管理も大事。
- 10月中旬第二次検定の受験
令和3年度より新問題が追加されましたが、従来通りの勉強でOKでした。
- 1月中旬合格発表
9:00から以下HPで公開されます。結果の書面は数日で届き、印紙をつけて合格証書を申請します。
- 2月中旬合格証書ゲット!
※参考:スケジュールは一般財団法人建設業振興基金のHPを参照した
申し込みから合格までの流れがつかめたでしょうか。なお、願書作成はちょっとした注意点があります。》【願書の書き方】注意点について
次に一次、二次それぞれに必要な勉強時間をご紹介します。
第一次検定(旧学科試験)に必要な勉強時間
気になる勉強時間ですが人によります。
経験年数や、所属(ゼネコンor専門業者)で知識レベルが大きく異なるからです。
全種目が対象なので幅が広くなりますが、ざっと以下の通りです。経験が少なめで専門業者なら+αを最大値で見て下さい。
過去問・問題集を使って7年分程度を2~3周するのに要する時間です。
最初の1周目がややしんどいですが、何とか進めると合格出来ることがわかってきます。一次は簡単であると見えてくると思います。
あとは残りの日程をふまえて、ご自分で+α分は調整して下さい。
第二次検定(旧実地試験)に必要な勉強時間
二次は記述式になり、論述(経験記述)もあって、急角度で難しくなります。
勉強時間は人によります。経験年数や、所属(ゼネコン or 専門業者)で知識レベルが大きく異なるからです。
ざっと以下の通りです。経験が少なめで専門業者なら+αを最大値で見て下さい。
過去問・問題集を使って10年分程度を4~5周します。
2~3周後、ご自分で+α分は調整してほしいです。

記述はどうしても不安になって過度に+αをしてしまうかもしれません。
施工管理技士・受験・モチベーションの維持方法

勉強方法以前に心構えが大事です。
モチベーション維持に役立つ情報をまとめます。
何かを得るには一定の犠牲が必要!
前記に勉強時間を紹介しました。
何かを得ようとすると一定の犠牲が必要です。つまり「毎日1時間×4~8ヶ月」程度を決意出来るかどうかです。
「その程度か!」と思える人はほぼ合格決まりです。
ベストセラーの「独学大全」によれば「上手くいくか否かは、テクニックでも効率でもなく、普段の生活の中で適切に時間を配分したかどうかによる」とのことです。
参考書籍 》独学大全【読書猿】
逆に言えばこの程度が調整出来ない、時間が作れない、難しい、、、と思うならば、やめたほうがいいかもしれません。
例えば、問題集を、朝食前に20分、お昼休み後に20分、その他空き時間や帰宅後に20分読む・・でいいのです。飲みにも行けるし、テレビドラマもみれます。決意なんて言葉は恥ずかしくなりますよね。
頭の良し悪しは関係ありません。これは実際に勉強をスタートすればわかります。
必要なのはコツコツ進める力だけです。

そうはいうものの、不安になる、躊躇してしまうのはよくわかります。
一次の最初30時間ぐらいがシンドいところです。以後は、これは行けるなと感触がえられるので、ここからモチベーションマネジメントは不要になるとも思います。
※時間配分やモチベーションはこちらの記事でも詳しく解説しています。
》不合格だった時に見直すべき4つのこと!
次にオススメの方法を紹介します。
合格後のメリットを再確認して未来の自分をイメージする
施工管理技士資格を取得に至った気持ちを突き詰めると、年収がアップするということですよね。
言っておきますが、確実に年収アップします!
その土台となるものは以下の通りです。挫けそうなときはこれらを踏まえて、充実している自分をイメージして下さい。
そして、実は目に見えないメリット・効果もたくさんあるんです。
》【迷っている】人に伝えたい!目に見えない6つのメリット
とある高校・農業土木科の新聞記事に勇気をもらう
2級の難易度はざっと1級の7~8がけです。そこまでの大きな差はない感じです。
そこでとある記事を一部抜粋します。香川県立石田高校の農業土木科3年生のほとんどが2級土木の一次検定にパスしたという記事です。
香川県さぬき市の学び舎で将来の郷土を担う人材を育てる香川県立石田高等学校。全国建設研修センター(CIC)が6月に実施した「2021年度2級土木施工管理技術検定」の第1次検定に、同校農業土木科3年の受検者全員が合格した。
https://www.kensetsunews.com/web-kan/614513

いや~、感心しました!問題集見ただけで諦める人に知ってほしい!
何度も書きますが、一次は何とかなります。
そして、一次に合格するということは、コツコツ勉強が定着したということ。次に「欲」が出てきます。「欲」を踏み台にすると、二次も見えてきます。
決断が全ての根本となるので丁寧に説明しました。以下から本題です。
施工管理技士・第一次検定・勉強法

第一次検定(旧学科試験)は4肢1択が主となるマークシートです。
令和3年度より1級は一部の問題で4肢2択や5肢2択問題などが追加され、その部分に関しては足切りもあります。
勉強法は過去問を7年分を2~3周でOKで、2周程度すると合格出来ることが実感できます。
次に詳しく見ていきます。
まず、過去問・問題集を手に入れる
過去問・問題集を入手して下さい。テキスト・参考書の類は不要です。
色々あって迷うと思うのですが、時間がもったいないので、業界定番で硬派で濃厚な一冊をおすすめします。地域開発研究所の過去問解説集です。
テキストがどうしてもほしいなら、同社の第二次検定の冊子に組み込まれているので一緒に購入して下さい。
第一次検定はまず合格できるので、コツコツやると決意が出来ているなら、二次の問題集も最初に買っておいて間違いないでしょう。
問題集が決まれば耳学するのも一つです。以下の記事も参照下さい。
過去問・問題集(7年分)を2~3周する

過去問・問題集の7年分を2~3周目指して計画します。
エビングハウスの忘却曲線は勉強・記憶の定番理論です。
これによれば、最初の1ヶ月は頭に入れてもどんどん忘れていきます。

実際も私も全く理解できず、覚えられずでした。でもこれでOKです。
そこで、1ヶ月、1周目あたりは、1年分を全部解いて翌年度に移行する【縦串方式】ではなく、分野ごとに攻める【横串方式】とします。
| 縦串 | 1年分(95問)をこなし、翌年の問題へ進む方式でサイクルが遅い |
| 横串 | カテゴリーごとの約15問(10~20問)をこなし、翌年の15問へ進む方式でサイクルが早い |
こうすると同系の問題に接するサイクルが早くなるので記憶が定着しやすくなります。
例えば土木は一般土木が15問、問題・解説を読むのに1時間程度。7年分は一日1時間で1週間で終了。4択問題は正答率25%ゼロ地点ですが、1週間で正答率45%ぐらいが見えてきます。「あっ!意外に行けそうだ」と思うのでモチベーション的にも横串方式は有効です。
忘却曲線によれば1ヶ月後程度から記憶の定着進み、1〜2週間程度は覚えているため、そこから縦串方式に変更すると前記に紹介したグラフのようにいい感じで記憶定着が進みます。
問題文も解説も、全く理解不能でもOK。とにかく問題を解いては解説を読む、この繰り返しでOKです。※あまりに意味が分からない時は用語検索程度は行います。
最初は問題別に出題傾向をざっくりつかめてくればOKなんです。
※第二次検定も同じように横串方式からスタートし、1ヶ月以後は縦串方式にします。
なお、選択問題がありますが、勉強段階で絞り込みはオススメしません。すべて勉強しておき、当日は簡単な問題を分野を問わず選んでいくイメージがいいのです。
2周目終了後、未経験の過去問題でセルフ模試をする
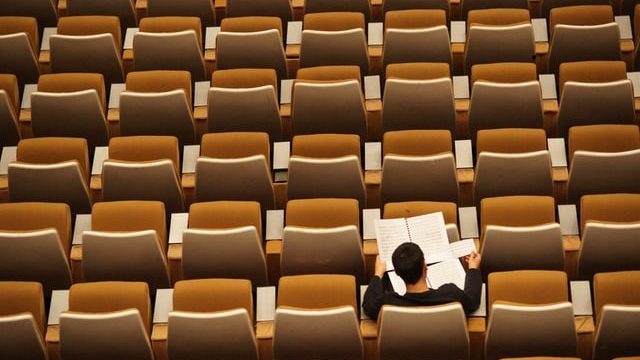
2周目・2ヶ月後は間隔をあけても問題ないため、年度毎に解いて行き(縦串方式)、合格点以上を意識していきます。
選択問題も選んでいき、正答率があがるか確認していきます。
2周終了して実力を実感できれば、未経験の過去問で実際の試験想定で解いてみます。これをセルフ模試とします。
直近3年以内ぐらいがオススメですが、基本どの年度でもOKです。
セルフ模試で合格ライン60%+遊びの10%で、70%以上超えたらOKです。
その結果をもとに後の勉強時間は調整し、試験当日が記憶のピークになるようにして下さい。
ラスト1か月は以下の記事も参照して下さい。
施工管理技士・第二次検定・勉強法

第二次検定(旧実地試験)は記述問題と、経験記述と大きく2つに分けられます。
一次と比較して難易度が急角度で上がります。
勉強法の構成は一次とほぼ同じですが、記述問題となる点が大きな違いです。自身の経験を記述する論述的問題もあり、そこでは減点されない工夫も必要です。
種目によっては、選択問題もあるので、合格点60%を狙ってうまく調整していきましょう。
まず、過去問・問題集を手に入れる
大きな流れは一次と同じですので、簡潔にまとめていきます。
問題集は業界定番で硬派で濃厚な一冊をおすすめします。地域開発研究所の過去問解説集です。
経験記述を準備する
経験記述は自信の実際の経験を記述する問題です。
減点されないためのに一定のルールがあります。過去問・解説集をよく読めば記載が可能です。
問題集の解答例等から自分の経験に合致する事例を取り上げテンプレートとします。
自身の経験から具体的数値などを加筆し、現場の臨場感を出します。出来た案は客観的視点で読み返し、ストーリー性があればOKです。
文書作成等に慣れていない人は、先輩等の経験者に内容を確認してもらうと良いです。これは必ずして下さい。
経験記述は準備さえしていれば8~9割はとれます。
なお、過去問事例集の引用は問題ありません。その際の注意点は以下にまとめました。
※自身の経験記述案は独りよがりになることも多いです。
もしも、第3者のチェックが社内で頼めない場合、格安サービスもあるので検討するもの一つです。例えばオススメは 独学サポート事務局です。

裏をとるのに、社内に有資格者がいなかったり、協力的でないならおススメかもしれません。社内とは言え気を遣う人、忙しい人もいますしね。
独学サポート事務局は実績も年数も申し分なく、色んなセコカンブロガーがオススメして信頼感があります。コスパも良好です。
※記述式問題に適した文房具を揃えると効率が上がります。以下を参照ください。
過去問・問題集(10年分)を4~5周する
第二次検定の記述式問題は、過去問・問題集の10年分を4~5周目指して計画します。
これも、記憶の定着を目的に、1ヶ月・2周目あたりまでは、年度ごとの縦串方式ではなく、分野ごとの横串方式で行きます。※前記、第一次検定の内容参照。
こうすると同系の問題に接するサイクルが早くなるので記憶が定着しやすくなります。
なお、種目によっては選択問題がありますが、勉強段階で絞り込みはオススメしません。全部勉強して、当日は簡単な方を選ぶという方針が良いです。
4周目終了後、未経験の問題でセルフ模試をやる
二次も一次と同様に未経験の問題でセルフ模試をします。
経験記述は丸暗記で行けるので80〜90%取れるとし、記述式問題が安全圏の60%とれているか確認します。

必要な勉強時間や繰返し回数は人によります。
セルフ模試のタイミングは自信がついてきたころで良いです。
配点は非公表ですが予測できます。次の5種目は詳しくまとめました。
》建築、土木、管工事、電気工事、電気通信工事
なお、色々と話題になる足切り点ですが、第二次検定ではありません。詳しくは以下にまとめました。
あとは運を天に任せて当日を迎えるだけです。当日の状況は以下を参照してください。
まとめ

施工管理技士はポイントを抑えれば誰でも合格出来ます。
1級の建築、土木、管工事に関してはピンポイントで細かく解説しています。以下もご参照下さい。
当手法は全ての資格取得に有効です。「資格といういわゆる肩書」は幅広くもつことで就職や昇進の際に差別化が出来ます。
より幅広く使えるように再構成したのが次の記事です。合格したら是非とも「次」を検討下さい。
》【資格・勉強法】忙しい社会人でも独学で合格が出来る理由










コメント